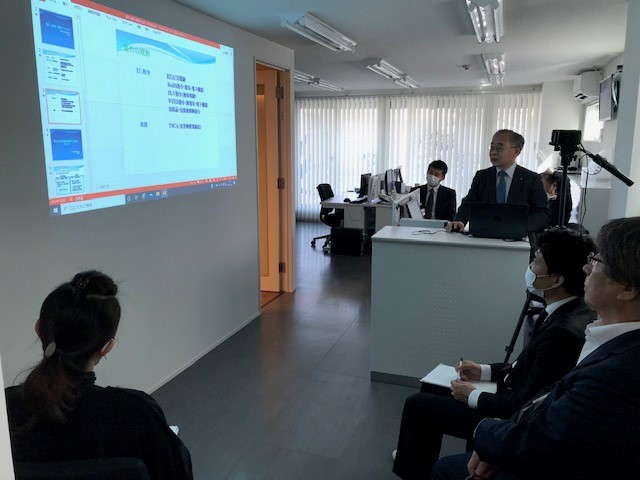リスクアセスメント後のリスク低減対策の優先順位をわかりやすく解説
「リスクアセスメントで化学物質のばく露が濃度基準値以上となっていることがわかったけれど、どう対策すればよいかわからない…。」とお困りの方もいらっしゃるでしょう。
リスク低減対策を検討する際は優先順位をつけることが大切です。
本記事では『化学物質管理者講習テキスト』の第7章に基づき、リスクアセスメント後のリスク低減対策の優先順位をつけた検討方法についてわかりやすく解説しています。
リスクアセスメント後のリスク低減対策の重要性
化学物質を取り扱う事業者では、リスクアセスメントとは別に従業員の健康を守るための対策義務があり、すべての従業員の化学物質のばく露を濃度基準値以下にしなければなりません。
リスクアセスメントを実施して、従業員のばく露が濃度基準値を超えるおそれのある作業を把握した後は、リスク低減対策が必須です。
もしリスク低減対策を怠った場合は、労働安全衛生法に基づき行政指導や罰則が課せられるリスクがあります。
それ以上に、大切な従業員の健康が損なわれる危険性が高まるため、リスク低減対策は確実に実施しましょう。
危険性に対するリスク低減措置の優先順位
リスク低減措置は以下の優先順位で検討することが大切です。
- 本質安全対策
- 工学的対策
- 管理的対策
- 保護具の着用
それぞれを具体的な例を交えて解説していきます。
1.本質安全対策
本質安全対策とは、化学物質の危険性や有害性の原因そのものを除去・低減することで、根本的にリスクを抑える方法です。
化学物質の使用中止やリスクの低い物質への代替などが当てはまります。
塗料を例にすると、溶剤系塗料から水性塗料や環境配慮型塗料に置き換えることが本質安全対策です。
2.工学的対策
工学的対策とは、有害な化学物質のばく露や労働災害のリスクを減らすために、設備や技術的な対策を導入する方法です。
化学物質に係わる機械設備の密閉化や局所排気装置の設置などが当てはまります。
局所排気装置・プッシュプル型換気装置などの塗装ブースの設置や、ロボット塗装・スプレーガンの遠隔操作などが工学的対策です。
3.管理的対策
管理的対策とは、化学物質のばく露リスクを減らすために、作業方法や手順の改善、教育の実施、管理体制の強化を行う対策です。
作業手順の改善やマニュアルの整備、教育訓練などが当てはまります。
塗料の適切な取り扱い手順のマニュアル化や、ラベルやSDSに基づく講習の実施などが管理的対策です。
その他にも化学物質のばく露時間の管理や有機溶剤の濃度測定による作業環境の監視なども管理的対策に含まれます。
4.保護具の着用
従業員に保護具を着用させることで、従業員の呼吸域の化学物質濃度を基準値以下にする対応です。
保護具は個人用であり、PPE(Personal Protective Equipment)と略され、安全靴や保護手袋、マスクなどが当てはまります。
ただ保護具を着用させれば良いという訳ではなく、個人に合った保護具を選択することが大切です。
保護マスクについては、マスクフィットテストで個人に最適なものを選択できます。
リスク低減対策はミドリ商会にお任せください
リスクアセスメントは化学物質の危険性や有害性から従業員を守るために実施します。
現場のリスクの見積り・評価が完了した後は、リスク低減対策を行い、従業員が安心して働ける環境を作りましょう。
ミドリ商会では本記事で紹介した4つの対策すべてをご提案できます。
お客様の現状をヒアリングさせていただき、最適な対策を一緒に考えていきますので、お気軽にお問い合わせください。