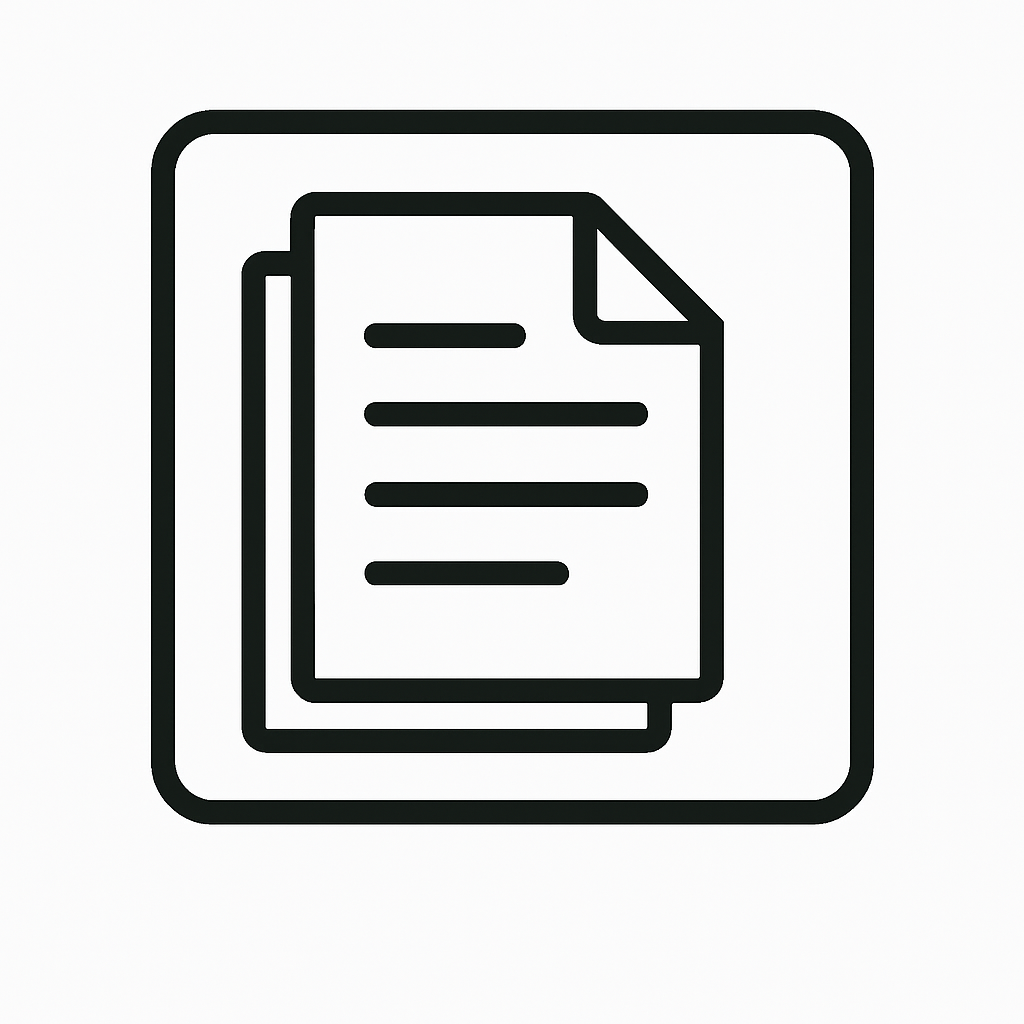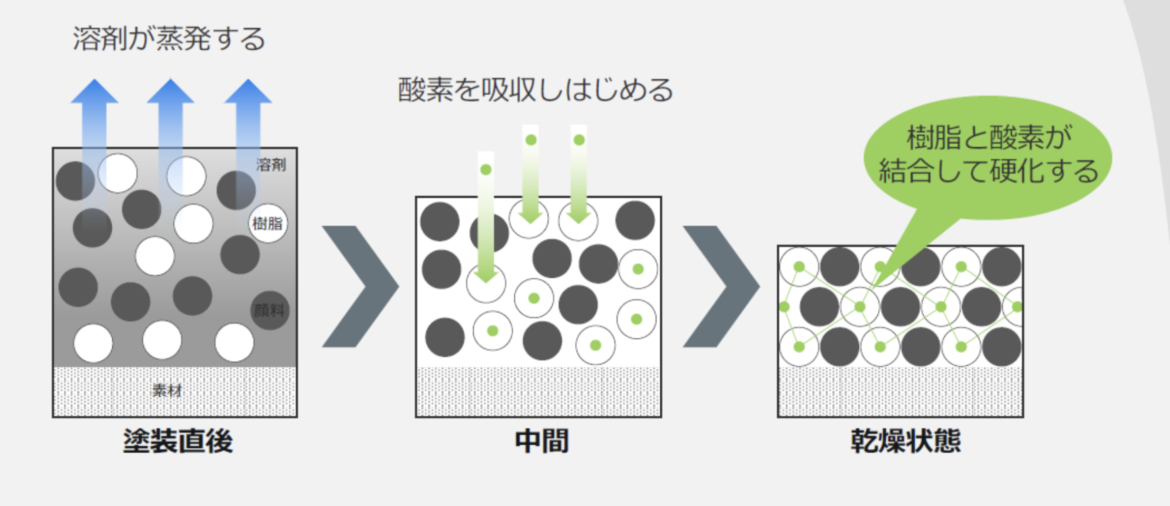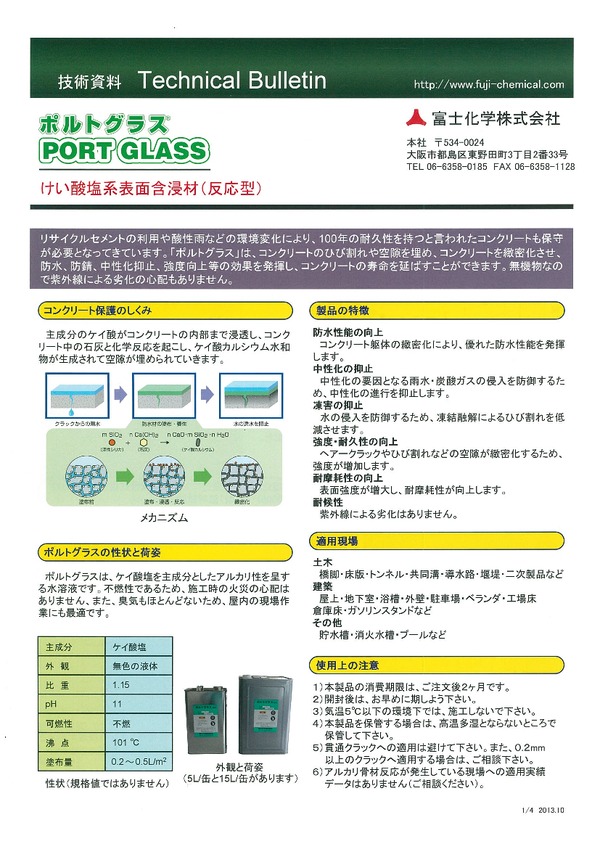健康診断は労働者の健康のために必ず実施しよう!特殊健康診断も解説
「化学物質を取り扱っていれば、特殊健康診断が必ず必要なの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
特殊健康診断が必要なのは特化則や有機則など特別規則で定められている化学物質を取り扱う場合ですが、対象外の化学物質でも健康診断を実施した方が良い場合もあります。
本記事では『化学物質管理者講習テキスト』の第9章に基づき、労働者の健康診断についてわかりやすく解説しています。
化学物質管理者が健康診断で担う役割
職場における化学物質管理の目標の一つは、化学物質による健康被害を起こさないことです。
化学物質の健康被害は急性中毒からがんなど早期では気付きにくい慢性疾患まで幅広いため、職場で取り扱う化学物質のばく露が引き起こす健康リスクをあらかじめ把握して、定期的な健康診断で当該疾患の兆候が認められないことを確認することが大切です。
化学物質管理者が健康診断で担う役割には、以下があります。
- 化学物質の種類とそれを取り扱う作業者の把握
- 化学物質が引き起こす可能性のある健康障害の把握
- 健康診断結果のフィードバック
ただし、健康診断の実施や事後措置については労働者の個人情報を多く含むため、産業医や守秘義務規定のある衛生管理者等が担当することが原則です。
化学物質管理者は医療職と連携を取り、健康診断に異常があった場合は作業環境管理対策の不備や化学物質のばく露がないか検証する必要があります。
特殊健康診断について
特殊健康診断とは、特化則・有機則などの特別規則で定められている化学物質を使用する事業場で働く労働者が対象となる健康診断です。
当該業務に従事する前の配置前健康診断、業務従事期間中の健康診断があり、発がん性がある一部の物質については配置転換後健康診断の実施が定められています。
実施頻度は原則として6ヶ月以内に1回です。
2023年4月からは有機則と特化則に関する特殊健康診断について、作業環境管理やばく露対策が適切に実施されていれば、実施頻度を1年に1回に変更できる緩和措置が取られています。
特化則、有機則に規定されていない化学物質の健康診断
特化則や有機則に規定されていない化学物質のうち、リスクアセスメントの対象物質については、リスクアセスメントの結果に基づいて労働者の意見を聞き、必要があれば健康診断の実施が必要になります。
リスクが許容範囲を超えていると判断された場合には、当該の化学物質の有害性を基にスクリーニング項目を含んだ健康診断を実施することが大切です。
リスクアセスメント対象物の健康診断を実施した場合は、記録を作成して5年間(がん原性のある物質については30年間)保存しなければなりません。
また受診した労働者に対しては遅滞なく健康診断結果を通知する必要があります。
ミドリ商会ならリスクアセスメントの代行が可能です
健康診断を実施するかどうかの判断材料となるリスクアセスメントの実施は事業者の義務ですが、他の業務が忙しくてリスクアセスメントが実施できないという企業様も多いでしょう。
ミドリ商会では『リスクアセスメント代行パッケージ』で通常業務が忙しい企業様に代わって、リスクアセスメントを実施できます。
リスクレベルの把握から労働者への周知までワンストップで対応可能です。気になる方はお気軽にお問い合わせください。